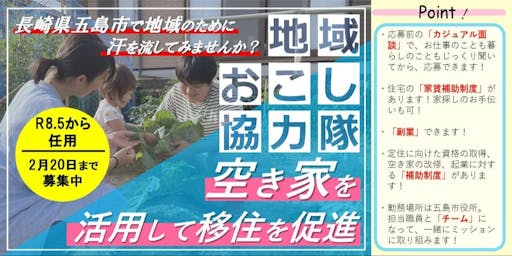海なし県の山の中!トラフグ学級の生徒たちと一緒に成長しませんか!トラフグ養殖を村の産業にする人を募集!!
最新情報
プロジェクトの募集が終了しました。
2022/12/29天川村は、紀伊半島の中央部の一番高いところに位置し、夏には避暑地として、秋には紅葉の名所として人気のある観光地です。ところが冬は他の季節と比べて観光客が減ってしまうことから、冬場に目玉となるような特産品が必要となると考えました。 そこで、目を付けたのが冬に最盛期を迎えるトラフグです。 トラフグは「フグの王様」とされており、てっちりは多くの人に愛されています。 天川村では同じ水を循環して養殖を行う「閉鎖循環式陸上養殖」を採用しており、現在3年の月日が経過しました。メディアにも取り上げて頂き、少しずつではありますが天川村でのトラフグ養殖が村内外に浸透してきました。4年目を迎える今年は養殖を行う水槽の数を増やし、2,800匹の稚魚を投入しました。目標である天川村の冬の特産品を目指し、着実に歩を進めております。
トラフグ学級の毎日
稚魚でやってきたトラフグたちは、1年半から2年かけて出荷できるサイズに成長します。その間は毎日、水質検査や餌やり、施設の清掃やメンテナンスを行います。水槽の中をぐるぐると泳ぎ回るトラフグたちは、時にはケンカをすることも。餌の食いつき具合などで様子を観察していると、だんだんとトラフグの体調などがわかるようになってきます。そのほか飼育計画をたてて体調管理を行い、定期的に歯切り作業や測定を行っていきます。気温や湿度によっても様子が変わるので毎日目が離せません。
〈1日のスケジュール〉 8:30~水質測定 9:00~清掃 9:15~餌やり 10:00~清掃 11:00~データの打ち込み 11:30~水質調査 お昼 13:00~機器メンテナンス 14:00~資料作成 15:00~清掃 15:15~餌やり 16:00 戸締まり
〈先輩隊員からの一言〉 生き物に興味がある方や、自ら学んでいこうとする探究心のある方が向いていると思います。まだまだ技術が確立されていない陸上養殖は毎日根気のいる仕事ですが、トラフグがだんだんと成長していく様子を見るのは面白さややりがいを感じられます。
□地域に仕事を生み出す取組 #特産品トラフグの養殖及び商品開発 #養殖事業計画の作成 #養殖施設の企画・立案 #施設管理者として施設の運営・監理等 #その他水産業振興・地域活性化事業に関すること 育ったトラフグは村内外の飲食店に卸す予定です。これからこの事業を一緒に育てましょ う。


天川村地域おこし協力隊 水産業支援担当募集概要
天川村役場産業建設課及び水産業(特にフグ養殖)に関わる施設を拠点として活動して頂きます。 ■総務省が定める条件不利地域以外に居住している方で、活動期間中、天川村に住民票を 異動し、居住できる方 ■概ね20歳以上、40歳以下の方 ■普通自動車運転免許を有する方 ■地域住民と協力しながら活性化活動に取り組むことができる方 ◆応募方法:応募用紙を天川村役場地域政策課に持参又は郵送してください。 ◆選考方法:申し込みのあった方から随時、書類審査及び個人面接を行います。 ※ 着任時期は応相談。年度途中の採用も可能です。 ◎そのほか募集詳細は天川村HPでご確認ください◎ https://www.vill.tenkawa.nara.jp/office/news/8955
このプロジェクトの地域

天川村
人口 0.09万人

天川村地域政策課が紹介する天川村ってこんなところ!
天川村は、奈良県のほぼ南半分を占める吉野郡の中央部に位置し、紀伊山地主部にあたる吉野山地の中心に立地しています。修験道発祥の地であり、宗教の発達と共に守られた自然と古くからの歴史・文化が残る村です。 村の玄関口は標高600m程に位置し、山を登ってくると川に沿って家々が並びます。 交通の不便さは解消されてきましたが、過疎高齢化が進み平成29年は1,500人ほどいた人口は現在1,300人程です。村内には診療所や郵便局、商店やガソリンスタンドがあり、近隣の町まで車で30分程度と山間地でも生活しやすい立地です。
このプロジェクトの作成者
天川村は、奈良県のほぼ南半分を占める吉野郡の中央部に位置し、紀伊山地主部にあたる吉野山地の中心に立地しています。 修験道の根本道場である大峯山「山上ヶ岳」や日本三大弁財天の一つである天河大辨財天社は、古くから信仰の地として多くの行者や参拝者が訪れる地域でした。そのため、歴史を通じて多くの文化資源があり、信仰によって守られた原生林や天然記念物、山岳・渓谷・森林の自然豊かな環境が観光資源となり、毎年約64万人が訪れます。地域に昔からあるもの、地域の伝統的な暮らしや文化に根ざしたものを拾い上げ、それらを活かしながら魅力的な地域づくりを進め、効果的に観光の魅力向上につなげようと取り組んでいます。 また農業・林業・水産業にも力をいれており、新たな特産物の開発、資源の活用の研究を行っています。 標高が高いことから、奈良市内などより気温が5度ほど低く、避暑地として好まれ、寒暖の差が激しいことから紅葉の名所でもあります。冬は雪景色を楽しめるなど、四季を通して違った魅力がありますので、シーズンを通して折々の自然を楽しめます。